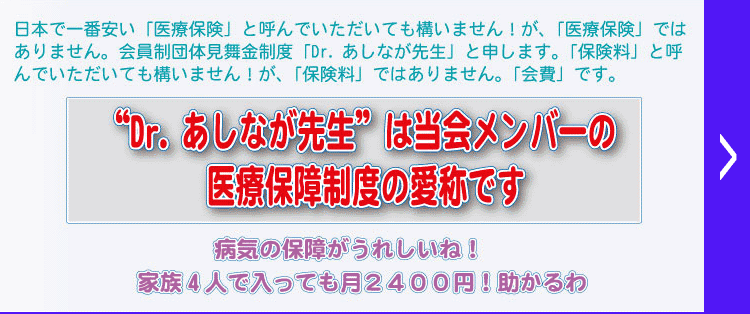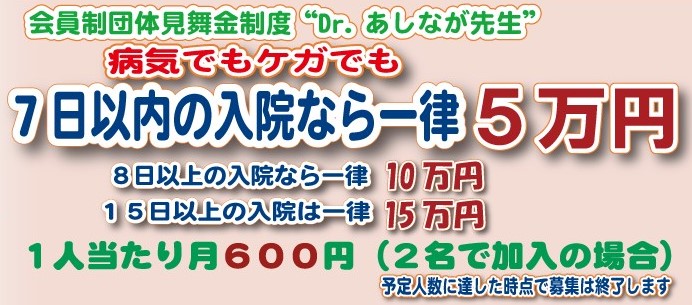1. 私の背景と経験
特に女性の中での格差には30年ほど前から深い関心を持ち研究を行っています。日本は先進国の中でも男女格差が大きい国であり、特に女性内部でも大きな差があります。男性の多くは正社員として働き続けますが、女性の場合、専業主婦という選択肢もあるため、無職の割合が高くなりがちです。年収が完全にゼロの女性の割合は全体の10%強にもなります。
女性の働き方は男性とは大きく異なり、無職、非正規雇用、正社員といった階層がはっきりと分かれています。こうした状況の中で、女性内部の格差はさらに顕著になります。私の著書『女性の階級』では、日本女性の間で見られる階級を30のグループに分けて詳しく分析しました。
この分析の基盤となったSSM調査は1955年から10年ごとに行われており、最新のものは2015年に実施されました。この調査で対象としたのは、日本全国から均等に抽出された20〜69歳の女性2885人で、全体の10.8%が「労働者階級の夫を持つパート主婦」でした。パート主婦は、主に扶養の配偶者控除の限度額(年収103万円)以内で働く非正規雇用の主婦です。
生活収入を夫に依存している一方で、家計を助けるために働いているこれらの女性たちの多くは、夫が家事や育児を手伝わないことからフルタイムで働くのが難しい状況に立たされています。
2. 男女間の格差と女性内部の格差
それに加えて、女性たちの間にも深刻な格差が存在しており、一部の女性は男性と比べてもさらに厳しい状況に置かれています。
特に専業主婦やパートタイムで働く主婦の生活は、絶えず変動する経済環境の中で非常に不安定なものとなっています。
男性の多くは正社員として雇用され、安定した収入を得ていますが、女性の場合は就労状況が多様であり、正社員、非正規雇用、専業主婦といったさまざまな形態が見られます。
特に専業主婦として家庭を支える女性は、離別や死別などのライフイベントが起きた際に再就職するのが極めて難しい現実があります。
これは、社会的な支援体制や再教育の機会が不足しているためで、多くの女性が経済的に厳しい状況に追い込まれる一因となっています。
男性が終身雇用やキャリアの一貫性を維持できるのに対して、女性は結婚や出産といった人生の節目でキャリアを中断せざるを得ないことが多いです。
このため、女性の間でも経済的な格差が広がりやすくなっています。
無職、非正規、正社員といった3つの階層に女性は明確に分かれており、それぞれの階層内でもさらに細かいグループ分けができるほど多様です。
著者の実施した調査によれば、最も多いグループは「労働者階級の夫を持つパート主婦」となっており、これが日本の女性の現実を如実に物語っています。
この「労働者階級の夫を持つパート主婦」というグループは、主に扶養の配偶者控除の限度額以内で働いており、収入は育児や家事の負担を減らすことが難しい環境に依存しています。
夫が家事や育児に協力しない場合、フルタイムで働くことはさらに困難です。
結果として、これらの女性は経済的な独立が難しく、夫の収入に大きく依存する生活を余儀なくされています。
このため、女性内部の格差はますます拡大し、一部の女性は非常に脆弱な状況に陥っています。
女性たちがもっと経済的に自立できる社会を目指すためには、性別による労働環境の違いを是正する必要があります。
特に、女性がキャリアを中断せずに継続できるような支援制度や再教育の機会を増やすことが急務です。
そして、男女共に家事や育児を分担する意識が広まることで、専業主婦やパート労働者の女性が直面するリスクを軽減できると考えられます。
3. 女性の働き方と収入状況
日本においては、依然として男女の働き方には大きな違いが見られます。
特に女性の間では、就労形態が無職、非正規、正社員の3つに分かれることが多いです。
この構造が、女性の内部での格差を拡大させる一因となっています。
日本の女性の約10%が完全に無収入という驚くべきデータがあります。
これは、専業主婦が一定数いることから来るもので、男性とは大きな違いです。
また、有職者の中でも女性の正社員と非正規の割合はほぼ半々となっています。
対照的に、男性の場合は正社員の割合が約80%と非常に高いです。
こうした背景から、女性の働き方には大きな課題が存在します。
特に、子供が小さいうちは専業主婦として家庭に専念する女性が多いですが、これは将来的なリスクを孕んでいます。
例えば、離別や死別といったライフイベントが発生した場合に、正社員として再就職するのは非常に難しいのです。
実際、離別後に正社員に復帰できる女性はわずか4%と言われています。
女性の働き方と収入状況には多くの課題が山積しています。
現状では、男性と同じようにキャリアを積むことが難しい環境が続いていますが、これを改善するためには社会全体での支援や政策の見直しが求められます。
4. SSM調査と女性の階級分け
この分け方は、まず職業の有無、次に所属階級、さらに夫の有無で決定されます。
例えば資本家階級や労働者階級といった具合です。
2015年のSSM調査によると、最も多かったグループは「労働者階級の夫を持つパート主婦」で、その割合は全体の10.8%に達しました。
SSM調査は1955年から10年ごとに実施されており、最新の調査では日本全国から均等に抽出された20歳から69歳の女性2885人が対象となっています。
パート主婦とは、非正規雇用でありながら扶養の配偶者控除限度額(年収103万円)以内で働く主婦を指します。
これらの女性たちは、家計を補助するために働いているが、収入の大部分は夫に依存しています。
子どもが少し大きくなり、時間的な余裕が生まれる一方で、夫が家事や育児に協力しないため、フルタイムでの就業は難しい状況です。
その結果、非正規雇用で働き続けるケースが多く見受けられます。
このように、女性の就業形態や家庭環境によって、社会内部での階級分けが細かくなされていることがわかります。
よって、女性たちがどのような状況に置かれているのかを理解する上で、SSM調査は非常に有用なデータを提供しています。
5. パート主婦の現状
このような状況で、パート主婦は経済的なリスクを抱えながら生活しています。夫が一家の主要な稼ぎ手であり続ける一方で、フルタイムでの雇用が難しい理由として、夫が家事や育児に協力しないという問題があります。多くの家庭で、夫が家事や育児を負担することは非常に少なく、その結果としてパート主婦が家庭内での責任を多く負うことになります。この状況は、特に小さな子供がいる家庭に顕著であり、母親が子供の世話をしながら働くことが前提となっています。
パート主婦の経済的リスクは離婚や夫の死亡などの不測の事態により一層増大します。夫の収入に依存している関係上、夫が働けなくなった場合や一家を支えることができなくなった場合、パート主婦は経済的に厳しい状況に置かれることになります。実際、離婚や死別後に正社員として再就職できる女性は非常に少ないことが現実です。この現象は、特に長期間にわたってパートとして働いてきた場合に顕著であり、スキルや職歴が不足していることが原因とされています。
このような背景から、パート主婦が直面する経済的リスクと家庭内の労働分担の問題は深刻です。これには、社会全体での理解と支援が必要であり、夫が家事や育児に対してもっと積極的に参加することが求められます。また、パート主婦がスキルアップやキャリア形成を支援するための制度やプログラムも必要不可欠です。このような支援が提供されることで、パート主婦が経済的に自立し、家庭内での役割分担も改善されることが期待されます。